カルシウムの多い食品をランキング形式で紹介します。
全食品からのTOP30と、食品ジャンル毎のTOP10を紹介。牛乳よりもカルシウムを多く含んだ食品が、たくさんランクインしてます。
また、カルシウムの吸収を促進する成分や、阻害する成分についても解説します。
それでは食品ランキングから見ていきましょう。
カルシウムの多い食品ランキング
はじめにランキングの簡単な説明です。
ランキング入りしている食品は、日常的に手に入りやすいものを優先して選びました。栄養成分については、「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」を参照しています。
また、ランキングにはカルシウムの他に、摂り過ぎるとカルシウムの吸収を阻害・排出してしまうナトリウムとリンの含有量も載せておきました。
ナトリウムは摂り過ぎに注意、リンはカルシウムの0.5〜2倍ぐらいの範囲で摂るのが理想です。
そのあたりに注意しながらランキングを見てください。
カルシウムの多い食品TOP30

※Ca=カルシウム, Na=ナトリウム
※食品100gあたりの成分含有量
※出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
| 食品名 | Ca (mg) |
Na (mg) |
リン (mg) |
|---|---|---|---|
| 干しエビ | 7100 | 1500 | 990 |
| バジル粉 | 2800 | 59 | 330 |
| 乾燥パセリ | 1300 | 880 | 460 |
| パルメザン | 1300 | 1500 | 850 |
| いりごま | 1200 | 2 | 560 |
| 脱脂粉乳 | 1100 | 570 | 1000 |
| たたみいわし | 970 | 850 | 1400 |
| 刻み昆布 | 940 | 4300 | 300 |
| 小アジ(唐揚げ) | 900 | 140 | 700 |
| さば節 | 860 | 370 | 1200 |
| カットわかめ | 820 | 9500 | 290 |
| 山椒粉 | 750 | 10 | 210 |
| チェダーチーズ | 740 | 800 | 500 |
| さくらえび(茹) | 690 | 830 | 360 |
| ゴーダチーズ | 680 | 800 | 490 |
| 凍り豆腐 | 630 | 440 | 820 |
| プロセスチーズ | 630 | 1100 | 730 |
| うるめいわし(干) | 570 | 2300 | 910 |
| カレー粉 | 540 | 40 | 400 |
| しらす干し | 520 | 2600 | 860 |
| 切干しだいこん | 500 | 210 | 220 |
| あおさ | 490 | 110 | 460 |
| 天然あゆ(焼) | 480 | 3900 | 160 |
| 紅茶 | 470 | 3 | 320 |
| いかなご(佃煮) | 470 | 2200 | 820 |
| カマンベール | 460 | 800 | 330 |
| わかさぎ | 450 | 200 | 350 |
| せん茶 | 450 | 3 | 290 |
| まいわし(干) | 440 | 1500 | 570 |
| 即席中華めん | 430 | 2500 | 110 |
全食品からカルシウムの多い食品をランキングにしました。
ランキング上位には、水分量の少ない乾物が並んでいますね。ただ、乾物はそれほど量を食べられないのが弱点です。
それ以外だと、チーズ、ごま、小魚あたりが扱いやすくて良さそう。バジル、パセリ、山椒など調味料にもかなり多く含まれています。使うときは多めに振りかけると良いんじゃないでしょうか。(^_^;)
乾物ばかり並べてもしょうがないので、もっと実用的な食品を種類ごとに見ていきます。まずは乳製品から。
カルシウムの多い乳製品TOP10

| 食品名 | Ca (mg) |
Na (mg) |
リン (mg) |
|---|---|---|---|
| パルメザン | 1300 | 1500 | 850 |
| 脱脂粉乳 | 1100 | 1500 | 850 |
| チェダーチーズ | 740 | 800 | 500 |
| ゴーダチーズ | 680 | 800 | 490 |
| プロセスチーズ | 630 | 1100 | 730 |
| カマンベール | 460 | 800 | 330 |
| モッツァレラ | 330 | 70 | 260 |
| ヨーグルト (無脂肪無糖) |
140 | 54 | 110 |
| ソフトクリーム | 130 | 65 | 110 |
| 普通牛乳 | 110 | 41 | 93 |
カルシウムといえば、やはり乳製品。だけど同じ乳製品なら、牛乳やヨーグルトよりもチーズの方が、カルシウムを多く含んでます。
牛乳やヨーグルトを大量に摂るよりは、チーズを少量食べたほうが効率的。ただしチーズはナトリウムも多いので加減が必要ですね。チーズの中ではモッツァレラが塩分も少なくていい感じ。
また、乳製品には乳糖とタンパク質が消化される過程で作られるカゼインホスホペプチド(CPP)が含まれていて、これがカルシウムの吸収に役立ちます。
乳製品はカルシウムを摂取するのにとても優れている食品。ところが詳しくは触れませんが、牛乳のリスクを気にしている人も多いと思います。その場合は、日本の伝統的な食品でもある魚介類が良さそうです。
カルシウムの多い魚介類TOP10

| 食品名 | Ca (mg) |
Na (mg) |
リン (mg) |
|---|---|---|---|
| 干しえび | 7100 | 1500 | 990 |
| 煮干し | 2200 | 1700 | 1500 |
| さくらえび | 2000 | 1200 | 1200 |
| さば節 | 860 | 370 | 1200 |
| うるめいわし(干) | 570 | 2300 | 910 |
| からふとししゃも | 350 | 590 | 360 |
| さば缶 | 260 | 340 | 190 |
| しじみ | 240 | 180 | 120 |
| しらす | 210 | 380 | 340 |
| ほっけ開き | 180 | 770 | 360 |
魚介類はイメージ通りカルシウムが豊富。なかでも骨や殻を丸ごと食べられる食材が凄いですね。
ところでランキングの一番最後に載っている「ほっけ開き」に注目してください。「ほっけ」って身はズッシリ詰まっているけど、骨は少ない魚ですよね。その割には、カルシウムが豊富です。
これには理由があって、実は魚のカルシウムって身の部分にも集まってます。正確には“筋隔”ってところで、魚の身に年輪みたいに入っている白い筋のことです。マグロの刺し身なんかをイメージして貰うと分かりやすいかと。
というわけで、魚は骨ごと食べないとカルシウム摂れないと思っていたらなら間違いです。アジやサバの身にもカルシウムは含まれていますが、「ほっけ開き」が一番豊富だし、食べやすいのでオススメです。
見てもらえば分かる通り、牛乳よりもずっとカルシウムが豊富。
[kanren postid=”2874″]
<参照>
社団法人全国海水養魚協会「ウォールドくんのお魚大百科」
熊本県海水養殖漁業協同組合「からだを作るお魚の栄養」
次は野菜を見ていきましょう。
カルシウムの多い野菜TOP10

| 食品名 | Ca (mg) |
Na (mg) |
リン (mg) |
|---|---|---|---|
| 切干しだいこん | 500 | 210 | 220 |
| パセリ | 290 | 9 | 61 |
| だいこん葉 | 260 | 48 | 52 |
| モロヘイヤ | 260 | 1 | 110 |
| しそ | 230 | 1 | 70 |
| ケール | 220 | 9 | 45 |
| みずな | 210 | 36 | 64 |
| つまみな | 210 | 22 | 55 |
| ルッコラ | 170 | 14 | 40 |
| こまつな | 170 | 15 | 45 |
意外なことに、野菜にもカルシウムは多く含まれています。
ランキングを見ると切り干し大根が圧倒的ですが、これは干してあるからであって、水に戻すとこまつなと同程度になります。
手に入り安いものであれば、みずな、つまみな、こまつな、このあたりが良いですね。これまた牛乳以上のカルシウムが含まれています。
もし栽培できるならケールが最高。地中海原産で“野菜の王様”と言われるケールは、栄養豊富でカルシウムも豊富。それにケールに由来するカルシウムは、牛乳と同じぐらい吸収率が良いらしいです。
最後に、野菜を選ぶときはシュウ酸にも十分に注意してください。詳しくは後述します。
<参照文献>
ファンケル研究開発「ケール由来のカルシウムは吸収がよい」
次は、毎日食べている人も多いと思われる豆類について。
カルシウムの多い豆類TOP10

| 食品名 | Ca (mg) |
Na (mg) |
リン (mg) |
|---|---|---|---|
| 凍り豆腐 | 630 | 440 | 820 |
| 油揚げ | 320 | 4 | 380 |
| がんもどき | 270 | 190 | 200 |
| きな粉 | 190 | 1 | 660 |
| 焼き豆腐 | 150 | 4 | 110 |
| 生湯葉 | 90 | 4 | 250 |
| 糸引納豆 | 90 | 2 | 190 |
| 木綿豆腐 | 86 | 59 | 110 |
| おから(生) | 81 | 5 | 99 |
| 絹ごし豆腐 | 57 | 14 | 81 |
毎日のように食卓に登場する豆類。その中でも“畑の肉”と呼ばれる大豆製品がランキングを占めています。
油揚げや豆腐なんかは毎日食べられるので、ぜひ積極的に摂りたいですね。糸引納豆とは普通に売っている納豆のことで、こちらもビタミンKなど骨を強くする成分が入っているのでオススメ。
ただし、大豆製品はリンが多めに含まれている場合があるので、リンの摂り過ぎには注意です。
最後にミネラルが豊富なナッツ類です。
カルシウムの多いナッツ類TOP5

| 食品名 | Ca (mg) |
Na (mg) |
リン (mg) |
|---|---|---|---|
| ごま(炒) | 1200 | 2 | 560 |
| えごま(乾) | 390 | 2 | 550 |
| アーモンド(炒) | 260 | – | 480 |
| ピスタチオ | 120 | 270 | 440 |
| くるみ(炒) | 85 | 4 | 280 |
スーパーフードとしても注目されるナッツ類。食物繊維やミネラル、ビタミンが豊富で、ぜひ積極的に摂りたい食品です。
ナッツ類のなかでも、カルシウムの含有量は「ごま」が圧倒的。手を加えるなら消化が良くなるよう、擦りおろして食べるのがオススメです。
アーモンドもなかなか凄いです。アーモンドはビタミンEなど、美容・健康効果に優れた栄養成分が豊富なので、こちらもオススメです。
[kanren postid=”2558″]
ところで食品に含まれているカルシウムは、その成分量をそのまま吸収できるわけではありません。
カルシウムは食品ごとに吸収率が違う
 カルシウムは食品ごとに吸収率が違います。
カルシウムは食品ごとに吸収率が違います。
だからカルシウムをたくさん摂取したつもりでも、実は足りてないなんてことがありえます(汗)
食品ごとに、どのぐらい吸収率が違うのかというと、ザックリした情報ですが以下になります。
[aside type=”warning”]食品ごとのカルシウム吸収率
- 牛乳:39.8%
- 小魚:32.9%
- 野菜:19.2%
出典:上西一弘ほか、日本栄養・食料学会誌vol51、259-299(1998年)
[/aside]
注意点があって、このカルシウム吸収率は、成人女性たった9名を試験した結果です。母数も少ないですし、参考程度にしておいてください。
また、牛乳が40%近くで野菜が19%となっていますが、例えば野菜のケール由来のカルシウムは、牛乳より優れた吸収率だという研究結果があります。必ずしも野菜の吸収率が低いわけではありません。
それでも想像よりは、カルシウムの吸収率が低いことが分かりますね。
このようにカルシウムの吸収率を下げてしまう原因って何でしょうか?
カルシウムの吸収を阻害・排出する成分
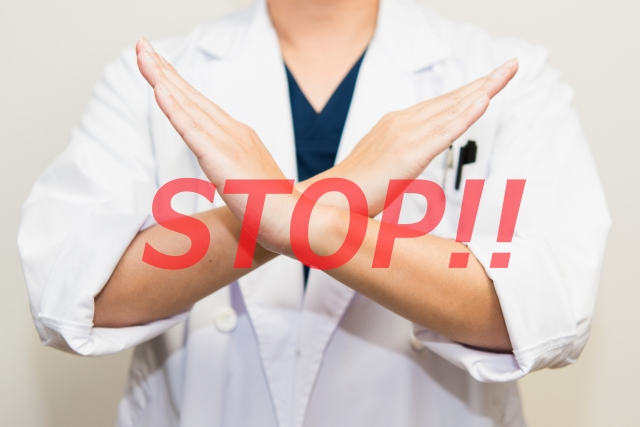
カルシウムの吸収率を下げてしまう原因は、食品に含まれている様々な成分です。どんな成分なのか見ていきましょう。
ナトリウム
ナトリウムは摂り過ぎると、尿と一緒に体内のカルシウムを排出します。
ナトリウムといえば食塩。参考までに食塩100gに含まれるナトリウムの量は39g(約40%)です。
厚生労働省の「ナトリウムの食事摂取基準」では、成人でも1日に摂取する目標値を食塩8g未満(ナトリウム3.2g未満)としています。
日本食は特に塩分の多い料理なので、食塩のとり過ぎには十分注意したいですね。
リン
リンは、カルシウムに対して多すぎても少なすぎてもダメ。カルシウムに対して、0.5〜2倍ぐらいの範囲で摂るのが適切です。
リンを摂り過ぎるとカルシウムと結合して、カルシウムが吸収され難くなります。
リンは肉類や加工食品、スナック菓子、清涼飲料水に多く含まれていたり、pH調整剤や乳化剤の内容物として使われることがあるので要注意。
現代人はリンを摂りすぎている傾向があるので、リンが多くなりすぎないよう食事のバランスに気を付ける必要があります。
シュウ酸
シュウ酸は消化中にカルシウムと結びついて、シュウ酸カルシウムとなって排出されます。だからといってシュウ酸を含む食品を食べるときに、カルシウムを食べないというのは間違いです。
カルシウムが不足するとシュウ酸は腸で吸収され、腎臓を経由して尿管に入ります。これが尿路結石の主な原因となります。
シュウ酸を多く含む食品を食べるときは、カルシウムも多く摂ることが大切。シュウ酸によりカルシウムの吸収は阻害されますが、尿中へのシュウ酸の排出を減らし尿路結石の予防になります。
シュウ酸を含む野菜は、煮ることでそのシュウ酸の7〜8割を水に流して、減らすことが出来ます。
<シュウ酸を多く含む食品>
- ほうれん草
- キャベツ
- ブロッコリー
- カリフラワー
- レタス
- たけのこ
- さつまいも
- バナナ
- チョコレート
- お茶(玉露、抹茶、煎茶)
- 紅茶
- コーヒー
- ココア
食物繊維
食物繊維を摂り過ぎると、カルシウムの吸収を阻害すると言われていますが、これは相当量とった場合で、普段食べる食事の範囲であれば全く問題ないそうです。
<参考文献>
下田妙子編集「臨床栄養学栄養管理とアセスメント編」
マリリングレンビル著「検証骨粗鬆症にならない体質」
NUTRI-FACTS「食物ナトリウム塩化物と疾病」
オーソモレキュラー.jp「カルシウム」
公益財団法人 骨粗鬆症財団「予防について」
次はカルシウムの吸収を促進する成分を見ていきましょう。
カルシウムの吸収を促進する成分

マグネシウム
マグネシウムは、カルシウムを吸収するのに欠かせない成分です。カルシウムとマグネシウムは、2:1のバランスで摂取するのがベスト。
マグネシウムが不足すると、カルシウムが骨に届かなくなります。さらに骨に蓄積しているマグネシウムを取り出し、同時にその数倍のカルシウムも取り出してしまいます。
カルシウムを摂取するときは、マグネシウムも忘れずに摂るようにしましょう。
マグネシウムが多い食品
※食品100gあたりの成分含有量
※Mg=マグネシウム, Na=ナトリウム
| 食品名 | Mg (mg) |
Na (mg) |
リン (mg) |
|---|---|---|---|
| あおさ(干) | 3200 | 3900 | 160 |
| ごま(炒) | 360 | 2 | 560 |
| アーモンド(炒) | 310 | – | 480 |
| 油揚げ | 150 | 4 | 350 |
| 全粒粉 | 140 | 2 | 310 |
| 木綿豆腐 | 130 | 59 | 110 |
| 玄米 | 110 | 1 | 290 |
| がんもどき | 98 | 190 | 200 |
| ごぼう | 54 | 18 | 62 |
| オクラ | 51 | 4 | 58 |
ごま・アーモンドなどナッツ類は、スーパーフードだけあって全てのミネラルが豊富。豆類もマグネシウムとカルシウムも豊富。毎日食べるなら、玄米・ごぼう・オクラあたりもオススメです。
ビタミンD
ビタミンDは小腸でカルシウムの吸収を助ける働きと、血液中のカルシウムを骨まで運ぶ働きがあります。
また、骨を作る働きをサポートします。
ビタミンDは日光に当たることで、皮膚からの合成も可能。紫外線のあたり過ぎは良いことがないので十分注意です。
ビタミンDが多い食品
※食品100gあたりの成分含有量
※D=ビタミンD, Na=ナトリウム
| 食品名 | D (μg) |
Na (mg) |
リン (mg) |
|---|---|---|---|
| しらす干し | 61 | 2600 | 860 |
| 筋子 | 47 | 1900 | 490 |
| 白鮭(塩鮭) | 23 | 720 | 270 |
| うなぎ蒲焼き | 19 | 510 | 300 |
| いわし蒲焼き(缶) | 17 | 610 | 290 |
| さんま | 14.9 | 130 | 170 |
| たちうお | 14 | 88 | 180 |
| 干し椎茸 | 12.7 | 6 | 310 |
| 卵黄 | 5.9 | 48 | 570 |
| まいたけ | 4.9 | 0 | 54 |
ビタミンDを多く含む食品は、魚介類が圧倒的に多いです。塩分のとり過ぎに気をつけつつ、週に何回かは魚を食べるようにしたいですね。また魚介類以外では、ナトリウムやリンが少なくて扱いやすい、まいたけがオススメ。
乳糖
乳製品に含まれる乳糖はカルシウムの吸収を助けます。
日本人の85%は乳糖不耐症といわれており、牛乳を食べるとお腹を壊してしまう人は、発酵食品のヨーグルトやチーズがオススメ。
ヨーグルトには牛乳と同じぐらい乳糖が含まれていますが、なぜか大丈夫な人が多いようです。チーズにほとんど乳糖が含まれていません。
カゼインホスホペプチド
乳製品に含まれるタンパク質の大部分がカゼインであり、このカゼインが消化される過程でカゼインホスホペプチド(CPP)となります。カゼインホスホプチペイドは、小腸でカルシウムの吸収を助けます。
<参考文献>
山田奈美著「つよい体をつくる離乳食と子どもごはん」
株式会社 明治「栄養成分編」
オーソモレキュラー.jp「カルシウム」
カルシウムの吸収を促進する成分も押さえたので、次は1日に必要なカルシウム量を確認しておきましょう。
1日に必要なカルシウム量

1日に必要なカルシウム量は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」が参考になります。
カルシウムの食事摂取基準
※推定平均必要量(mg/日)
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1〜2歳 | 350 | 350 |
| 3〜5歳 | 500 | 450 |
| 6〜7歳 | 500 | 450 |
| 8〜9歳 | 550 | 600 |
| 10〜11歳 | 600 | 600 |
| 12〜14歳 | 850 | 700 |
| 15〜17歳 | 650 | 550 |
| 18〜29歳 | 650 | 550 |
| 30〜49歳 | 650 | 550 |
| 50〜69歳 | 600 | 550 |
1日に必要なカルシウム量は年齢ごとに違っていて、ピークを迎えるのは12〜14歳の中学生のとき。それ以降は大して変化しません。
骨を蓄えて骨量が最も増えるのも中学生のときなので、カルシウムが不足しないよう十分に気をつけたいですね。
骨量がもっとも蓄積される時期は男子 13~16 歳、 女子 11~14 歳であり、とくに、思春期前半にカルシウム蓄積速度は最大になり、この 2年間に最大骨量の約 1/4 が蓄積されることが示されている。
1日に必要なカルシウム量は分かりました。
はたして日本人はカルシウムを十分に摂れているんでしょうか?
日本人はカルシウム不足
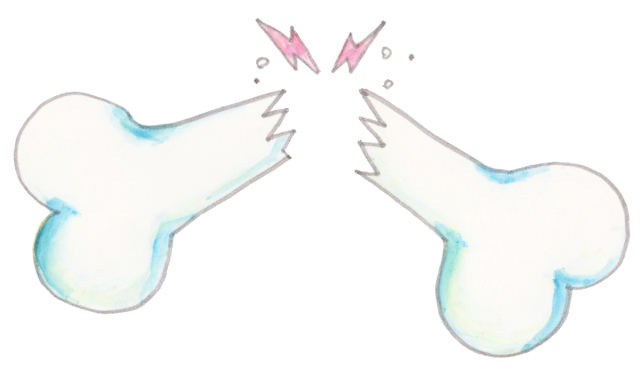
厚生労働省の「平成26年国民健康・栄養調査結果の概要」と「日本人の食事摂取基準(2015年版)」によると、日本人は全ての年代でカルシウムが不足しています。
カルシウム不足を解消するためには、どの食品をどれぐらい食べれば良いのでしょうか?
<中学生男子の場合>
◆小松菜
850mg(カルシウム必要量) ÷ 170mg(小松菜100gのカルシウム) = 5
小松菜の場合は1日あたり500g ⇛ だいたい10〜13束
※小松菜1束=30〜40g
◆牛乳
850mg(カルシウム必要量) ÷ 110mg(牛乳100gのカルシウム) ≒ 8
牛乳の場合は1日あたり800g ⇛ 牛乳びん4本 or 紙パック1本
※牛乳びん=200ml
◆木綿豆腐
850mg(カルシウム必要量) ÷ 86mg(木綿豆腐100gのカルシウム) ≒ 10
木綿豆腐の場合は1日あたり1000g ⇛ 豆腐3丁
※豆腐1丁=300g
◆ごま
850mg(カルシウム必要量) ÷ 360mg(ごま100gのカルシウム) ≒ 2.4
ごまの場合は1日あたり240g ⇛ 大さじ26杯
※ごま大さじ1杯=9g
◆プロセスチーズ
850mg(カルシウム必要量) ÷ 630mg(プロセスチーズ100gのカルシウム) ≒ 1.3
プロセスチーズの場合は1日あたり130g ⇛ キャンディーチーズ9個
※キャンディーチーズ1粒=15g
こんな感じで、1つの食品に置き換えて考えると、トンデモな量になってしまいます。ですのでバランス良く、いろいろな食品からカルシウムを摂るしかありません。
ところでカルシウム吸収率は気にしなくて良いのでしょうか?
食品ごとのカルシウム吸収率は気にするべき?

既にカルシウムの吸収率は、食品ごとに違ってくることを解説しました。
ですので1日に必要なカルシウム量を考えるときも、その吸収率を計算しないとかなと思ったのですが、その必要は無いようです。
性及び年齢階級別 の基準体重をもとにして体内蓄積量、尿中排泄量、経皮的損失量を算出し、これらの合計を見かけ の吸収率で除して、推定平均必要量とした
カルシウムの推定平均必要量を求める計算式には、既に吸収率(25〜40%)が含まれていました。ですので食品に含まれるカルシウム量だけを考えればOKですね。
まとめ
カルシウムの多い食品ランキングと、カルシウムの吸収を阻害する成分・促進する成分について紹介しました。
乳製品と魚介類は、イメージ通りカルシウムが豊富でしたね。乳製品では特にチーズが豊富でオススメでした。魚介類の場合は、意外なことに「ほっけ開き」にもたくさん含まれていることが分かりました。
さらに意外だったのは豆類や野菜の中に、牛乳よりもカルシウムを多く含んでいる食材があったことです。ただし、野菜を選ぶときはシュウ酸に気をつけたいですね。
シュウ酸を多く含むほうれん草などの野菜を摂るときは、カルシウムもたくさん摂ることが重要です。
その他カルシウムを摂るときは、ナトリウムやリンを摂りすぎないようにすることも大切です。
カルシウムが豊富で、毎日の食卓で使いやすい食品は、
- ごま
- アーモンド
- こまつな
- みずな
- プロセスチーズ
- 木綿豆腐
- 油揚げ
- ほっけ開き
このあたりがオススメ。
また、カルシウムの吸収率を上げる、マグネシウムとビタミンDも積極的に摂りましょう。マグネシウムは、ごまやアーモンドから、ビタミンDは魚やまいたけ等からも摂れます。
このようにカルシウムを多く摂るためには、その他の栄養成分にも気を付ける必要があります。そういったことを考えると、カルシウムの豊富な魚介類とか豆類をたくさん使う伝統的な日本食を食べるのが一番効率よさそうです。
ただし日本食は塩分が多いので、塩分は控えめに。乳製品は補助的に食べれば良いのかなと。
日本人は1日に必要なカルシウム量が十分に摂れていないということなので、積極的にカルシウムを摂って、健康な身体を作りたいですね。
毎日のカルシウムを食事から摂る自信の無い人は、以下のサプリもオススメ。カルシウム、マグネシウム、ビタミンDの栄養機能表示もあり、カルシウムの吸収率についてもしっかり考えられています。



コメント
大変勉強になりました。大変失礼ながら、タイトルは乳糖と思いますが、乳頭になっています。見た瞬間、理解不能でした。誤入力ではないでしょうか?
中国語医療通訳者、漢方と薬膳スタイリストなど認定資格を持ており、今、登録販売者資格対策勉強中です。私は間違いましたらお許しください。
米川さん、コメント有難うございます!
ご指摘どおり、誤入力です。。お恥ずかしい限り。
医療通訳や漢方などの資格を沢山お持ちで凄いですね。
記事の内容が、少しでもお役に立てば幸いです。
ご指摘有難うございましたm(_ _)m